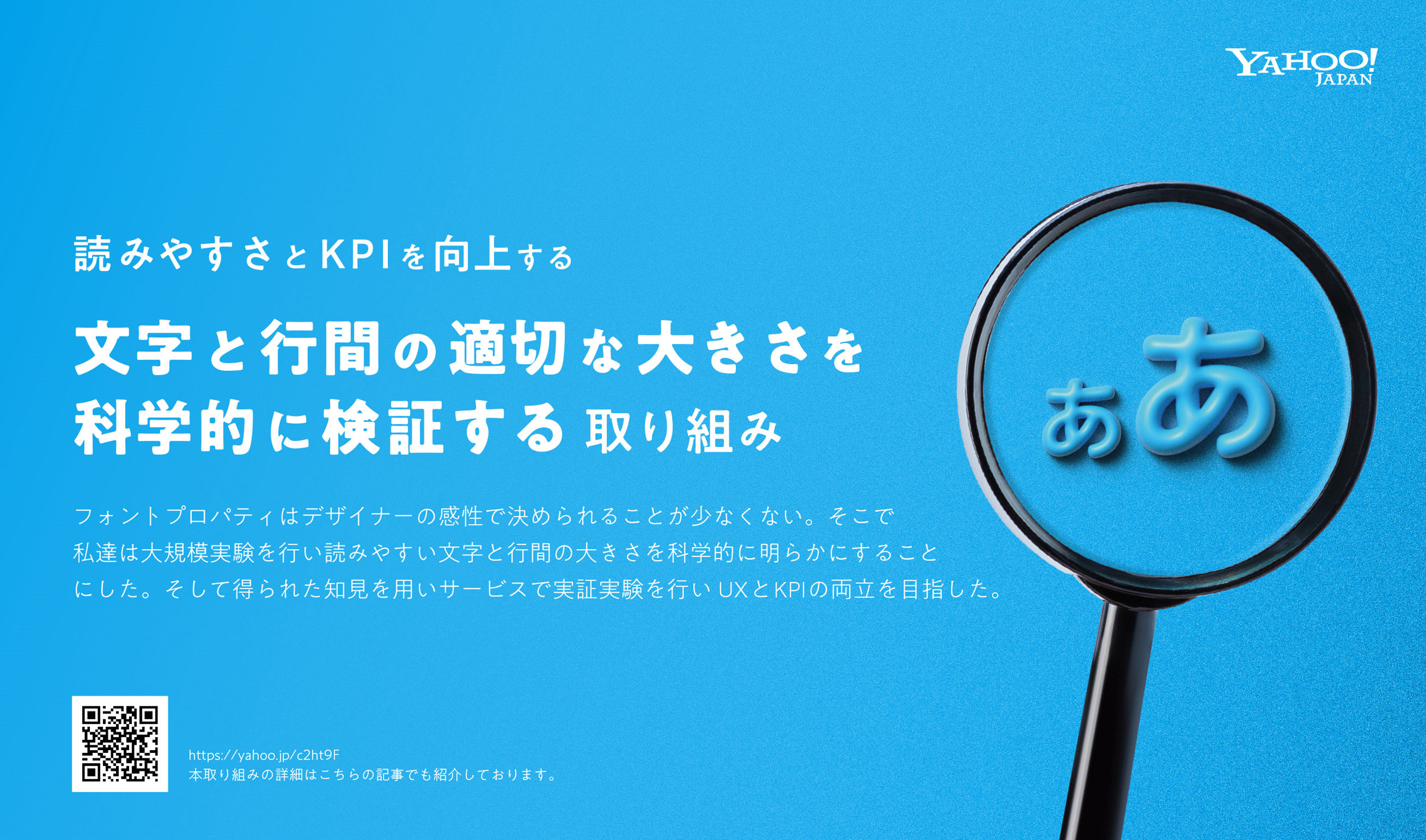多摩美生は設計力や実装力など、いくつものスキルをプラスアルファで持っている
LINEヤフー株式会社

2023年10月にヤフー株式会社やLINE株式会社などが一つになり誕生した日本最大級のテックカンパニー。コミュニケーションアプリ 「LINE」やポータルサイト「Yahoo! JAPAN」などを運営する。
https://www.lycorp.co.jp/ja/
2024年6月更新
多摩美生がプロデューサーを務めたフォントに関する研究が、
サービスのKPI向上に貢献

町田宏司さん
2003年|情報デザイン卒
LINEヤフー株式会社
デザイン統括本部 UXD本部
本部長
LINE とヤフー が統合したことで、所属するデザイナーは500人以上 になりました。そのなかには多摩美の卒業生も大勢含まれており、UIデザイナーやブランドデザイナーなど、それぞれの部署で活躍しています。卒業生の実績は数え切れないほどありますが、たとえば月間174億PVを超える規模で非常に多くのユーザーが日常の中で「文章を読む」という行為が行われるサービスで、現在私がデザイン責任者を務めているYahoo!ニュースのフォントプロパティに関する大規模実験もその一つです。スマートフォンでコンテンツを見る際に、ユーザーが最も読みやすい文字の大きさと行間のサイズを調べ、さらにKPI(重要業績評価指標)にどんな影響が出たかを実験したのですが、多摩美卒業生の鈴木さんがこの研究のプロデューサーを務めました。その結果、心理的負荷も低く視覚的なバランスも保たれ、さらにサービスの事業KPIにも良い影響をもたらす文字サイズと行間サイズを導き出すことができました。アカデミックな研究は社会実装されにくい面があると言われていますが、この実証実験の成果はアカデミック、ビジネス両面での価値を見いだすことができ、これは当社にとってだけではなく他社、社会、多くの人の体験を豊かにする標準を見いだせたとも言えると思います。
仕事で多摩美の卒業生と関わる機会も多いですが、彼らと接していて感じるのが、ビジュアルのアウトプット力だけでなく、設計力や実装力など、いくつものスキルをプラスアルファで持っているところです。先ほどの大規模実験も、プロデューサー本人が横断的にさまざまな領域のスキルを持っていたからこそ実現したことです。もちろん社会に出てから研鑽を積んできた部分もあると思いますが、得た知識を複合的に活用するというベースは、学生時代に培われたものだと感じます。

デザイナーの採用活動に携わるなかで、美大生全体の実力は年々高まっていると感じています。採用プロセスの中で拝見させていただくポートフォリオ のクオリティも、数年前に比べて格段にアップしました。加えて実際の「現場」を知っていることが、今、新たな強みになっています。現場に赴いて直接観察したターゲットの様子や生の声を聞いて、課題解決のプロセスを経験したことがある人は、そうでない学生と比べて、提案の裏付けとして机上の空論ではない分ソリューションの解像度が非常に高いです。
多摩美の卒業生は学生時代に産学官連携の活動を経験している人が多いので、ビジネスという複雑でリアリティのあるフィールドで活躍が期待できますね。
プロダクトの開発にはデザインとプログラム技術、両方の理解が重要。多摩美にはそれをサポートする環境がある

鈴木 健司さん
2006年|大学院情報デザイン修了
LINEヤフー株式会社
データグループ DS統括本部 LINEヤフー研究所
現在は全社のプロダクト品質や生産性の向上を支援する部署と、最新のインタラクションデザインに関する研究を行う部署の2つに所属しています。ユーザーにとってより見やすかったり、より操作しやすいデザインに関する研究を行っています。またその知見を全社のデザイナーやエンジニアに還元し、プロダクト品質や生産性の向上を目指しています。
高校時代はCGや映像表現に興味があり、幅広く学びたくて多摩美に入学しました。授業の課題はもちろん、演劇部活動などあらゆる表現を追求するなかで、「時代の進歩に自分の表現が全然追いついていない。テクノロジーをちゃんと理解し、表現を広げたい。」と感じるようになりました。そして表現の“道具”として扱えるよう、プログラミングの習得に取り組み始めました。大学院では現在のライブ動画配信アプリのような、配信者と視聴者が交流することで構築される放送番組のデザインとシステムの実装を行いました。ここで、自分のテーマを見出し研究する楽しさを知ったことが今につながっています。
いまプロダクトの開発において、デザインと技術、両方の理解が求められ始めています。実際に、両者が高度に融合したサービスが多く登場しています。もし、インタラクションデザインをやる上で「もっと発想を広げたい」と感じている人がいたら、ぜひプログラムの習得をお勧めしたいですね。きっと世界が広がるでしょう。一人で最新テクノロジーやIT技術を習得するのは難しいですが、多摩美にはサポートしてくれる人や十分な設備が整っていたので、私はこの両方を広く深く学ぶことができました。振り返ってみると、自分に何が必要かに気付けたことが大事なポイントだったと思います。学生時代のあらゆる経験が、就職後に大いに生かされています。