考えをビジュアル化してイメージを共有し、まとめあげていくコミュニケーション能力の高さで抜擢される
オリンパス株式会社
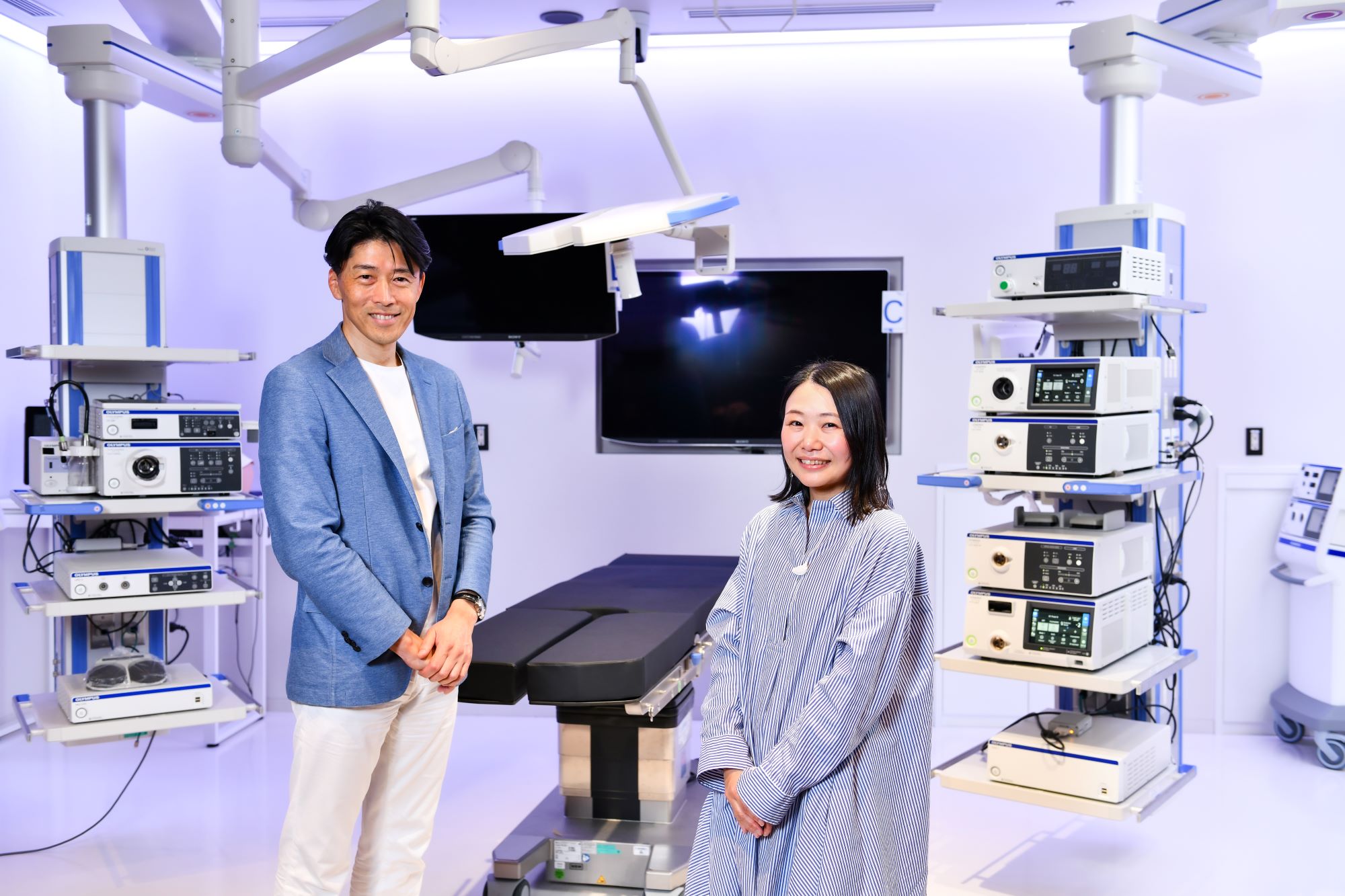
1919年に顕微鏡の国産化を目指して創業。2019年より光学機器メーカーからヘルスケア領域に専心し、イノベーションと価値創造に取り組むグローバル企業へと進化を遂げる。病変の早期発⾒や診断、低侵襲治療に役立つ最適なソリューション・サービスの提供を通じて、医療⽔準向上への貢献を目指す。
2024年6月更新
医療現場でのトレーニングによる「体験価値」が最終的にデザインへとつながり、活躍の場を広げている

谷尾聡さん
オリンパス株式会社
Vice President
クリエイティブセンター長
当社は現在、世界の医療事業者、そしてその先にいる患者様の安全性を担保することを目指すグローバル・メドテックカンパニーとして、消化器内視鏡システムや手術室のシステムインテグレーションなどの内視鏡事業、処置具のラインナップ拡充や呼吸器科など多様なデバイスの開発を行う治療機器事業を軸に展開しています。我々が所属するクリエイティブセンターも、医療専門のデザインチームです。2022年からはドイツとアメリカにも拠点を作り、世界の仲間たちと一緒にさまざまな製品やサービスを開発しています。
大学で医療デザインを学ぶ機会はそうないかと思いますが、我々も会社に入ってから基礎知識を学び、医療従事者の方々と接点を持って経験を積んでいきました。医療の現場で手技を模擬体験させてもらい、どういう難しさがあるのか、どんな痛みがあるのかなどを体験し、解析します。その一連の「体験価値」といったものが最終的にデザインへとつながっていきます。当社に在籍する3人の多摩美卒業生もそうしたトレーニングを経て、活躍の場を広げています。
多摩美生に共通する強みは、新しいことにチャレンジするマインドです。現在、多摩美卒業生のうち、1人はプロダクトデザイン専攻出身ですが、現在はさらにGUI(Graphical User Interface)にも活躍の場を広げており、2人は製品開発のコンセプトワークを担っています。開発の上流工程で「誰にどういった価値のあるものを提供するか」を具体化する重要なポジションです。医療従事者やエンジニア、研究開発、マーケティングなど各部門のスペシャリストが集まるなかで、プロジェクトの円滑な運営をファシリテートする業務を行っています。

2人をコンセプトワークの担い手として抜擢したのは、皆が頭のなかでふわっと考えていることをビジュアル化してイメージを共有できること、各部門の個性の異なるメンバーと対話を重ね、まとめあげていくコミュニケーション能力が高いことからです。おそらく大学時代に幅広く学び、引き出しをたくさんもっていることが今に生きているのだと思います。語学力も高く、グローバルの仲間からの信頼も厚いです。戸井田さんも相手の懐(ふところ)にスッと入って、相手の困りごとを聞いて、咀嚼(そしゃく)して、「こうですかね?」と解決案を提示することに長けています。チームを運営していくうえで、とても大切な能力です。そうした自分の強みをしっかりと持っている人は、これからの社会でも求められていくのではないでしょうか。
デザインの思考プロセス自体に価値があり、それを多摩美で当たり前のように学んでいたのは貴重な経験だった

戸井田真希さん
2004年|情報デザイン卒
オリンパス株式会社
Creative Center Tokyo Studio 1
Senior Manager/UX Designer
現在は主に次世代の内視鏡やそれを取り巻くシステム全体に関わる開発上流のデザイン活動を推進するという仕事をしています。医療機器はだいたい10年スパンでリリースしていくので、長い視点で医療の将来に思いをはせ、「そのときの社会はどういう医療を必要としているか」という、全くかたちのないところからのスタートになります。マーケティングや研究開発などのスペシャリストたちと切磋琢磨しながらディスカッションをして、そこでの議論や生まれたアイデアを図解してビジュアル化したり、プロトタイプを作って医療従事者のかたに現場で試してもらって意見をいただいたり、トライアンドエラーを繰り返す、そのルーティンを回していくというのが楽しいですね。いろんな知見を得て、皆の思いがかたちになっていく過程に大きなやりがいを感じています。
「デザイン思考」や「デザイン経営」といった言葉をよく聞くようになりましたが、具体化してユーザーや関係者の真意を探りながら方向性を示せるのはデザイナーの強みで、そのプロセス自体に価値があると思っています。それを大学時代に当たり前のように学んでいたのは、あらためて貴重な経験だったと思いますね。2年生の後期からインタラクションデザインを選択して農業のデザインを学んだのですが、1週間の農業体験をしながら農家さんの課題をヒアリングする機会もあり、現場での経験や当事者の声をデザインに生かす大切さは、そのころから身に染みていたように思います。
現在のポジションに就く際、最初は不安な部分もありましたが、「挑戦すれば見える世界も違ってくるのではないか」と思い、周囲の理解やサポートもあって、「じゃあ、やってみよう!」となりました。私は皆を引っ張っていくというよりは、皆の思いを聞いて前に進める「サーバント(奉仕)型」で、プロジェクトが円滑に進むようにコミュニケーションを考えますが、それも大学で学んだ「場のデザイン」や「空間のデザイン」と捉えると、自分にできることはあるのではないかと思って日々取り組んでいます。

学生時代は将来自分が今のような仕事をするとは全く想像していませんでした。社会の要請だったり会社の変化だったりに適応していった結果、たどりついたという感じです。「目に見えないものをデザインするのが情報デザインだ」ということは在学中に教授からよく言われていたことですが、今、まさに自分に求められている役割なのかなと感じています。
